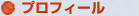今年度第1回目の保護者講座を23日(土)に行いました。
今年度のテーマは「大人に効く思考力・試行力」です。
この「思考」と「試行」とは、もうひとつの「至高」と合わせて、私が授業でもしばしば口にする言葉です。
今の生徒たちは「たった一つの正解」にたどり着くこと、しかも最短距離でたどり着くことに価値があると教え込まれてしまっています。
たしかに学校の授業や考査、入試問題などでは「作為的に」たった一つの正解を作り出すことはできますし、そのようにして作られた「問題」に対して、素早く、正確にたどり着くための技術を習得させることもできます。
しかし、この「技術」は実社会に出てからは、例えばシミュレーション力として発揮する機会はあるとしても、実際にはあまり役に立つとは思えません。なぜなら、仮に正解が「たった一つ」であるとして、それがすでに分かっているのなら、社会ではそれを「前提」として利用するだけだからです。
その意味で私の授業では、生徒たちは与えられたイシューについて自分自身で思考し、それをグループでお互いに発表しあい、学びあいを通して試行し、最後に至高の思考ルートを共有することが求められています。
実はこのことは学校教育だけでなく、家庭における教育においても重要な観点であると私は考えています。たしかに親は子供より人生経験が豊富であり、先を生きる存在ですが、その親であっても実際に経験しているのは「一つの」人生に過ぎず、そこから得た価値観も一つです。
また相手がいくら子供、高校生であるといっても、そこには確固たる人格が存在します。人格を持った人間が生きていくうえで、明らかに間違った生き方はあるとしても、たった一つの正解は存在しないだろうと、私は考えています。
おそらくこの考えには、多くの大人たち、保護者のみなさまも共感してくださると思うのですが、実際に子育てをしていくと、事はそう簡単ではありません。よその家庭の子育てについては客観的な視点を持てる大人でも、自分の子供のことになると180度違った視点を持つことも珍しいことではないのです。
******************************************************************************
前置きが長くなりましたが、このように、私を含めて「悩める大人たち」が集まって、いろいろ考えていきましょうというのが、この講座のコンセプトなのです。
対象となるのは全学年の保護者のみなさまなのですが、今回は会場の都合もあって先着90名で実施しました。申込期間は2週間とったのですが、3日目には満席となってしまいました。


最初のトピックは「あなたの日本語、本当に大丈夫?」
しっかりとした思考のベースには、しっかりとした言語力、ツールとしての日本語力が不可欠です。講座の途中では『論理エンジン』OS1を使って、保護者のみなさまの日本語力をチェックします。
ここで保護者のみなさまが受けるインパクトは相当のものがあります。苦笑いをなさる方もいれば、「学生の頃、国語は得意だったのに…」とつぶやく方もいらっしゃいます。そして、このインパクトは講座へのモチベーションを一気に高めていきます。
そこで「言語・認識・コミュニケーション」へと話が移っていきます。
やや堅苦しい内容になりますが、この後で取り上げる「ソーシャル・スキル」への伏線として欠かせないトピックです。

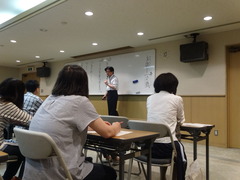
講座のまとめは、「言わねばわからぬ親になりましょう」
なんでも先回りして、子供の「育とうとする芽」を摘み取っていないか、そのことについての思考のきっかけを共有して講座を終了としました。
******************************************************************************
わずか80分間程度の短い講座でしたが、事後アンケートには嬉しいお言葉をたくさん頂戴し、開講してよかったと実感させていただきました。
ご多忙の中、ご参加くださった保護者のみなさま、ありがとうございました。
また、先着に間に合わず、お断りしてしまった多くの保護者のみなさま、誠に申し訳ございませんでした。
第2回の講座は2学期に行う予定です。
次回も、よろしくお願いいたします。
今年度のテーマは「大人に効く思考力・試行力」です。
この「思考」と「試行」とは、もうひとつの「至高」と合わせて、私が授業でもしばしば口にする言葉です。
今の生徒たちは「たった一つの正解」にたどり着くこと、しかも最短距離でたどり着くことに価値があると教え込まれてしまっています。
たしかに学校の授業や考査、入試問題などでは「作為的に」たった一つの正解を作り出すことはできますし、そのようにして作られた「問題」に対して、素早く、正確にたどり着くための技術を習得させることもできます。
しかし、この「技術」は実社会に出てからは、例えばシミュレーション力として発揮する機会はあるとしても、実際にはあまり役に立つとは思えません。なぜなら、仮に正解が「たった一つ」であるとして、それがすでに分かっているのなら、社会ではそれを「前提」として利用するだけだからです。
その意味で私の授業では、生徒たちは与えられたイシューについて自分自身で思考し、それをグループでお互いに発表しあい、学びあいを通して試行し、最後に至高の思考ルートを共有することが求められています。
実はこのことは学校教育だけでなく、家庭における教育においても重要な観点であると私は考えています。たしかに親は子供より人生経験が豊富であり、先を生きる存在ですが、その親であっても実際に経験しているのは「一つの」人生に過ぎず、そこから得た価値観も一つです。
また相手がいくら子供、高校生であるといっても、そこには確固たる人格が存在します。人格を持った人間が生きていくうえで、明らかに間違った生き方はあるとしても、たった一つの正解は存在しないだろうと、私は考えています。
おそらくこの考えには、多くの大人たち、保護者のみなさまも共感してくださると思うのですが、実際に子育てをしていくと、事はそう簡単ではありません。よその家庭の子育てについては客観的な視点を持てる大人でも、自分の子供のことになると180度違った視点を持つことも珍しいことではないのです。
******************************************************************************
前置きが長くなりましたが、このように、私を含めて「悩める大人たち」が集まって、いろいろ考えていきましょうというのが、この講座のコンセプトなのです。
対象となるのは全学年の保護者のみなさまなのですが、今回は会場の都合もあって先着90名で実施しました。申込期間は2週間とったのですが、3日目には満席となってしまいました。


最初のトピックは「あなたの日本語、本当に大丈夫?」
しっかりとした思考のベースには、しっかりとした言語力、ツールとしての日本語力が不可欠です。講座の途中では『論理エンジン』OS1を使って、保護者のみなさまの日本語力をチェックします。
ここで保護者のみなさまが受けるインパクトは相当のものがあります。苦笑いをなさる方もいれば、「学生の頃、国語は得意だったのに…」とつぶやく方もいらっしゃいます。そして、このインパクトは講座へのモチベーションを一気に高めていきます。
そこで「言語・認識・コミュニケーション」へと話が移っていきます。
やや堅苦しい内容になりますが、この後で取り上げる「ソーシャル・スキル」への伏線として欠かせないトピックです。

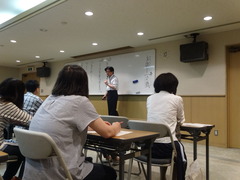
講座のまとめは、「言わねばわからぬ親になりましょう」
なんでも先回りして、子供の「育とうとする芽」を摘み取っていないか、そのことについての思考のきっかけを共有して講座を終了としました。
******************************************************************************
わずか80分間程度の短い講座でしたが、事後アンケートには嬉しいお言葉をたくさん頂戴し、開講してよかったと実感させていただきました。
ご多忙の中、ご参加くださった保護者のみなさま、ありがとうございました。
また、先着に間に合わず、お断りしてしまった多くの保護者のみなさま、誠に申し訳ございませんでした。
第2回の講座は2学期に行う予定です。
次回も、よろしくお願いいたします。